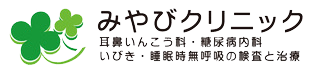睡眠時無呼吸症候群とは
睡眠時無呼吸症候群は、主に気道(呼吸をするときの空気の通り道)が狭くなっていることを原因に、睡眠中に呼吸が止まったり低呼吸になったりする疾患です。
いびきもその症状の一つですが、心臓や脳をはじめ全身に影響を与え、さまざまな病気の原因となります。
ちなみに、1時間で5回以上止まると睡眠時無呼吸症候群とされ、1回に1分間止まるという方も少なくありません。
なかには2分止まっているという患者さまもいらっしゃいます。
気道が狭くなる原因としては、主に、
- 筋力の低下(加齢)
- 舌が重い(肥満)
- 顎が後退している・扁桃肥大がある も報告されています。

こんな症状ありませんか?
- いびきをかく
(家族から「いびきがうるさい」と言われる) - いびきが10秒以上止まることがある
(家族から「いびきが止まっていることがある」と言われる) - 何度もトイレに行きたくなる
- 寝汗をかく
- 寝相が悪い
- 寝起きに喉が乾燥している・喉が痛い
- 日中、倦怠感や眠気がある
- 頭が重く感じることがある
- めまいが起こることがある
- 集中力がない
睡眠時無呼吸症候群が及ぼす影響
睡眠時無呼吸症候群によって、さまざまな病気が引き起こされたり悪化が促進されたりし、職場などで社会的な影響を与えることも少なくありません。
全身・ほかの疾患への影響
睡眠時無呼吸症候群は、寝ている間に酸欠状態を起こすため、少ない酸素を全身にめぐらそうとして心臓や血管に負担がかかります。
この状態が長い間続くと、さまざまな生活習慣病の合併症を引き起こす可能性があります。
社会的な影響
良質な睡眠が得られないため、日中の眠気や倦怠感、集中力の欠如などを感じやすくなります。
仕事のパフォーマンスが落ちるだけでなく、居眠り運転や機械の操作ミスなどに繋がり、大きな事故を引き起こしてしまう危険性も高まります。

リスクが高い合併症
- 高血圧
- 脳疾患【脳卒中(脳梗塞・脳出血)】
- 心疾患【心筋梗塞・狭心症】
- 糖尿病 特に、脳卒中や心臓疾患は、発症リスクが通常の4~5倍高まることがわかっています。
- 認知障害
- 発達障害 も報告されています。
また、睡眠時無呼吸症候群による、
治療の方法
治療では、睡眠時の呼吸をサポートする装置を用いる方法がメインとなり、代表的な「CPAP(シーパップ)」や「マウスピース」などがあります。
しかし、患者さまの症状によっては、手術が必要となることもあります(その際は、適切な手術ができる医療機関をご紹介しています)。
睡眠時無呼吸症候群の原因や程度によって検討・選択していきます。
CPAP(シーパップ)
眠っている間に専用マスクを装着し、鼻から空気を送り込んで睡眠中に気道が塞がらないようにするという治療機器を使います。症状が中度~重度の方の治療方法です。
具体的には、睡眠中に1時間で20回以上呼吸が止まっているという方が対象となります。

マウスピース治療
1時間に20回未満の方は、より気軽に取り組めるマウスピース治療の対象となります。
歯科でご自身専用のマウスピースをつくっていただき、眠るときにそれを装着します。
マウスピースによって下顎を持ち上げ、気道を広げるという方法です。
当クリニックは、マウスピースを製作する歯科クリニックとも提携しています。
外科的手術
大人の睡眠時無呼吸症候群で手術が必要なケースはあまり多くはありません。
喉や顎に外科的な処置をすることで気道が確保できるという方などは、手術ができる医療機関をご紹介しています。
高度肥満が原因という方も、外部医療機関の「肥満外科」と連携・紹介という流れで、胃の縮小など適切な手術を受けていただく場合があります。